| 全画面で読む | |
| さぎ草伝説 3 | |
| 「九人の女房の嫉妬と悪企み」 城中の花と愛された常盤の方の妊娠の報せは、いやが上にも諸人の注目することとなりました。 頼康卿をはじめとして淀殿や宿将等は、お家の万歳とばかりに温かい眼差(まなざ)しを注ぐのでした。 一方、今まで殿の寵愛を受けて、お側近くに仕えていた九人の女房たちは、誰からも顧みられないくやしさと怒りが日ましに募ったのです。 たまたま一堂に会した折り、女房等の中で年長の「玉ノ井」は、日ごろの不満を「常盤の方が御所に来て以来、私達に殿のお呼びも絶えたばかりか、下々の者にまで無視されているようである。 今更美しさを競うわけにもいかないが、なんとか昔の栄華を取り戻したいものである。 何かよい思案はないものか」と、嘆きとも、恨みともつかぬ言葉をはけば、気性の強い「舟橋」が後をついで、「一昨日などは、殿様と同じ台の床の中、昼夜別たぬ睦まじさは、羨やましさを超えて憎らしい。 もしも若君誕生となれば、御台所(みだいどころ)と仰がれよう。こうなった上は、我が身がどんなになろうとも、常盤を害せずには生きられようか」 聴き入る女房ひとり一人の胸に、めらめらと嫉妬の炎が燃え上がり、悪事加担が誓われたのです。 その悪事とは、今城中の注目を集めてもてはやされている美男美女の二人、つまり内海掃部と常盤の間にあらぬ噂を流して、頼康卿のもとから遠ざけようというものです。 この悪だくみは、年長の玉ノ井を中心にあらゆる機会を捕らえて実行されることになりました |
|
| 「美丈夫・内海掃部(うつみかもん)のこと」 「世田谷城の花が常盤の方ならば、美男の掃部は紅葉よな」と噂された内海掃部は、十七歳の折り頼康卿自らが元服の冠を授げ、将来を期待した美丈夫でした。 ある日のこと掃部は、城中で一通の手紙を拾いました。 その文は女房船橋の下女から近習の下部市若にあてた色恋文でした。 掃部の厳しい注意は当然のことでしたが「以後悔い改めれば他言はしない」と言う情けある言葉も空しくこの下女の胸には含む恨みが多く残りました。 一方掃部は、さ細いなことと気にもとめず忘れ去り、相変わらず殿の寵愛を一身に集め、皆々から親しまれる日々を送っていました。 だが、この一事が身をも家をも滅ぼす原因になろうとは、神ならぬ身の知る由もなかったのです。 こんな事件があったことを露知らず、折りにふれて頼康卿は、「掃部は、器量と言い才知と言い彼に過ぎる者はない。 しかも父伊部の長い間の勲功は、共々我が家の宝である」と、顔をくずして繰り返すのでした。 この言葉を受けて常盤の方も、心から親しみをこめて、この御所内は勿論(もちろん)のこと小田原・鎌倉の諸侯にまでもその名が聞こえ、美男の掃部を女性達は「まぶしきことよ」と噂をしています。と褒(ほ)めちぎりました。 しかし、この偽(いつわ)らぬ言葉が、後の災いになろうとは思いも寄らぬことでした。 「女房達の悪計とざん言」 戦乱相次ぐ世の中にあって、関東の雄である小田原北条家は、吉良氏にとって親密な同盟の間柄でありました。 折りから、城主氏康公の病篤しとの知らせに、頼康卿自ら多勢の家来を引き連れ、見舞いに出掛けました。 旅を重ねて、藤沢の宿に着いた時の事です。 卿のそば近くに宿直の任についていた掃部の懐から、以前常盤の方に与えた秘蔵の袱紗(ふくさ)と、その服紗にそえた一首の和歌が、卿の目の前に落ちたのです。 卿が目ざとく拾いあげて見れば明らかに常盤の方の筆で、 「おもいあまる涙は色にいずるとも 袖のしがらみ浮名もらすな」 と、ありました。 卿の怒りは心頭に達して、早速掃部に厳しい尋問が加えられましたが、もとより身に覚えのないこととて掃部は答えに窮し、ただ詫びるばかりであったのです。 一夜が明けましたが激怒は益々つのり、卿は関加賀守(せきかがみかみ)に内海一族に閉門蟄居(ちっきょ)を厳しく命じて、小田原城に入りました。 |
|
| 小田原城に逗留六・七日の間、この時ぞとばかりに玉ノ井は、さも真実のように掃部と常盤のあらぬ秘事を耳に入れたのでした。 加えて熊沢入道も召される度に、玉ノ井の言葉に味方する有り様でしたから、なんでたまりましょう卿の怒りは頂点に達してしまいました。 このことは早くも御所に伝えられ、淀殿の知るところとなりました。淀殿の問いに答える常盤の方は、「神にかけて身に覚えありません」と、強くその潔白を申し開きをしました。 淀殿もそれを知り頼康卿に伝え無実を訴えましたが、既に聞く耳を持たないまでに激情していたのでした。 |
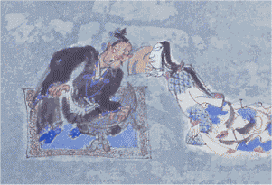 |
| 「内海父子の最後」 刻々と知らされる最悪の状況の中に、逃れる手段はないと覚悟した内海父子は、家来や妻子を小田原へ避難させると、伊予・掃部そして従弟の鈴木藤三郎の三人で屋敷に篭り、上意を待ったのです。 君命により、関加賀・田中出羽・同孫八・朝比奈喜右衛門・藤田弥五郎等いずれも一騎当千の者が討っ手に選ばれました。 昨日までの同僚を討つの心重く、内海の屋敷に駆け付けてみたものの、堅固な備えに討ち入ることができず、焦った田中孫八は雑兵の肩に乗り、塀に上がるやいなや、たちまち藤三郎の繰り出す槍に太股を刺され、どっとばかり落ちて呻く始末です。 これではならじと大門.小横・くぐり戸を一気こ破ろうとしましたが、豪勇の三人に切り立てられて果たすことはできないばかりか、関加賀・田中出羽まで深手を負うしまつで攻め倦(あ)ぐんでいたのです。 この状況はすぐさまお城に伝えられました。 対策が協議されている時、大声で加勢を申しでた者がありました。 大場入道景茂の孫「新左衛門吉隆」年十六歳であります。 あまりの若さに卿はためらいましたが、再三の願いに遂にこれを許しました。 内海屋敷に着いた吉隆は、大声で姓名を名のり開門を呼び掛けました。 これを聞いた掃部は「若蔵め何用」とばかり槍(やり)を構えて扉を開きました。 すると吉隆ただ一人、刀に手もかけず堂々と入り、落ち着いた態度で、「両人とも静かに、掃部殿にはこの度思わぬ勘気を蒙ったとは言え、君恩は山よりも重く、海よりも深い。たとえ筋の通らぬこととは言え、君命とあれば潔く死を選ぶのが誠の武士の道ではないか。その上に罪なき同僚を疵付けることは天の道にそむくものである」と、若者ながら道理に叶う言葉に内海父子は屈しました。 父伊予は何を思ったのでしょう、つと奥へ引き下がりました。 残る掃部と藤三郎は呆然と立ち尽くすのを見て吉隆はすかさず刀を抜き掃部の首を打ち落としたのです。 掃部この時二十一歳、盛りの花は哀れにも、無実の罪にはかなく散ったのでした。 一瞬のの出来事にうろたえる藤三郎の耳もとへ「伊予殿を討ち取り貴殿の罪を逃れたまえ」と、吉隆はささやきました。 はっとして身構える藤三郎、そこへ伊予が引き返して来ました。 我が子の死を見て吉隆に飛び掛かるのを膝に切り付け、たじろぐところを罪を逃れようとした藤三郎が首を打ち落としました。その藤三郎も吉隆に討たれて、敢(あ)え無い最後を遂げたのです。 この吉隆の抜群の働きは、御目付役の松下新蔵の確認のもとに頼康卿に報告されました。 卿は上機嫌で討手の一同を迎え入れました。 特に吉隆には褒美として太刀一振を授けたばかりか、官位を豊前守として四家老に加え政務の重役の任を与えたのです。 これを聞いた人々は家門の誉れ、世の手本と誉めはやしました。 |
|
| 鷺草伝説4へ | |
| ちょっと歴史に戻る | |