| 全画面で読む | |
| さぎ草伝説 終章 | |
| 「内海父子の怨霊のこと」 頼康卿は一時の激情に駆られて常盤を死に至らしめましたが、それが無実の罪であったと知ったとき、激しい自己嫌悪に陥りました。 思い起こすのは愛しい常盤と過ごした楽しい日々です。部屋に閉じこもり、食も細く、折々涙ぐむ主の姿に、世田谷城はひっそりと静まり返りました。 その折りも折り、七月九日の早朝より無気味な響きを先触れに、御所に激しい震動が繰り返し起きたのです。 「あれよ、あれよ」と騒ぐ間に、山崎の辺りより白鷺が群がり来て鳴き叫ぶこと著しく、何事か異変を予告するかのように人々の不安を掻き立てました。 すると突然、内海の屋敷からすさまじい黒雲が吹き上がり、蓮誉尼の庵(いおり)の後ろから流れる水は、紅を流したかのように若林・山崎の辺りの草を、みるみる血の色に染めたのです。 あまりの奇怪に、卿も驚き慌てて、諸山の高僧を集めて様々に祈祷を試みました。 |
|
| 香煙けむる祈祷の最中、不思議や不思議、玉ノ井のはした女が突然にもの狂いに狂って駆け回り、「我は鷺の宮の神霊なり。お前達は三寸の舌をもって罪なき者を殺し、殊に若君まで失うこと、天の罪逃れがたし。 常盤の方には露些(いささか)も曇りなく、身は服紗より事件となり、内海父子を滅ぼしたことは許しがたい。 元々服紗を掃部が所持していたことは、この女の妹が藤沢宿の遊女であり、女房どもに言い含められ、掃部が宿直の夜、旅の疲れでまどろむ時に人知れず服紗を袖に入れておいたもの、また歌の筆は掘江某の妻女で以前常盤に仕えて筆跡を良く知る者の偽筆である。 掘江某と親しい船橋ノ局がこの歌を書くことを頼み、某は何気なく書いたものである。更に服紗は、船橋の下女が盗み出したものである。掃部をこのように憎んだ訳は、この下女が下部の市若と言うものとひそかに取り交わしていた文を掃部が拾い注意して玉ノ井に返した。 |
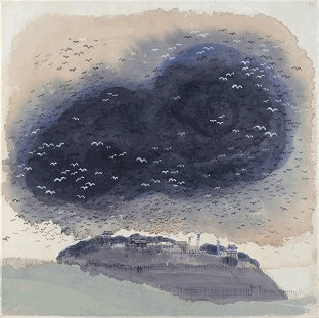 |
これが主君の耳に入ることを恐れてのことである。罪を犯した者共いちいち責め殺さずにはおくものか」と、絶叫して、どっとばかり倒れたが、又立ち上がり掃部の声で数々の恨みを述べ、罪なくして死んだ無念の一語を書いて投げました。 投げられた書は明らかに掃部の筆であったのです。余りのことに人々は呆然(ぼうぜん)とし、特に頼康卿の驚きと心痛は計り知れないものがありました。 「女房達の死罪のこと」 御所中鳴動の怪奇な事件は終わりました。この後直ちに下女が神がかって口走った真相の糾明(きゅうめい)がはじめられたのです。 ここで、家老筆頭の江戸遠江守は、はじめよりこの事件に関係することを遠慮して家にとじこもっていたのです。その理由は、掃部の母が自分の妹であったからに他ありません。 それが、掃部の死が無実のものであったと知って七月二十四日早々に御所に上がり、四家老をはじめ主立った面々を残らず集めて協議に及んだ後、女房達をはじめとして下部市若を厳しく糾明したのです。掘江の妻女も出て、船橋から頼まれた事実を述べたことによって、一同たまらずにことごとく罪を白状したのです。 又、大平出羽守は去年病死につき、常盤の兄の清九郎を呼んで、卿自ら無実の罪に陥れたことを、深い後悔と共に詫(わ)びれば、清九郎は謹しんで、「君として臣を討つことに何の恨みがありましょうか、ただ内海・鈴木と時の流れを共にしたことは運命と諦(あきらめ)残念に思います」と、潔(いさぎ)よく申し上げました。 一方、女房達十三人は浅はかな考えから罪なき者を殺害させた大罪を償い、併せて内海父子や常盤の方への供養の為と、周防上野の知行所若林村において、残らず処刑され、上馬までの間に築かれた十三塚の名前のみ、今は残されているのです。 「常磐の霊 供養のこと] 一陣の嵐にも似た日夜が過ぎて、世田谷城はようやく落ち着きを取り戻していました。 庵にあって静かに読経(ときょう)に過ごす蓮誉尼は、ある日常盤の方を偲び、形見の御守袋を開きました。 中には薬師如来と仏舎利が入っていたのです。 これを捧げ持ち淀殿を訪れました。 願いはこの度の騒動で命を落とした人々の追善供養に一寺を建立して戴きたいと言うものでした。 この願いは直ちに受け入れられ、若林村の女房達処刑の地に、御本尊を薬師如来として、「舎利山香林庵」が建てられました。 なお、これら供養に関連して、御胞衣を洗った所を尼沼、この水の流れに架けられた橋を常盤橋と名付けて、長く後の世に残したと言うことです。 ある人、常盤を偲び一詩を作り霊に捧げました。 城中第一ノ常盤ノ妾 艶々タル面容ハ月華ヲ欺キ 君ハ他二勝リテ比翼ヲ語ル 謹ニ倚リ野ニ死ス尼渟涯 一方、この事件の処理の中で内海家の再興が着々と図られ、小田原の福島家に養子となっていた左近を呼び戻し、家系を縦がせることになりました。 世田谷に帰った左近は直ちに下部市若を請い受け、父と兄の仇を討ったと言うことです。 しかしまだ城中一同の胸に、晴れやらぬものが残されていました。 それは非業の死を遂げた名もなき若君の魂を慰めることです。 ある日、四家老がお城の総意を代表して、若君慰霊の為の一社創建を御所に進言しました。 これが許されて昔八幡社が祀られていましたが、今は中絶している旧跡の地、馬引沢中郷神戸に社(やしろ)を建て、若宮八幡と名付けて崇めたのです。 また、常盤の方の供養として、法華経千部を書写し、弁財天を勧請(かんじょう)してお堂に祀りました。 これがすなわち田中弁財天(現常盤弁財天)であります。 「終わりの章」 夢となく現つともなく、美女の語る物語に聞き入っていた旅の僧空山は、突如として舞い上がった夜烏(夜鴉)のけたたましい一声に、ふっと我に返りました。 目の前の人影は幻のごとく掻き消えて、夕闇はいよいよ濃く、あたりの森を黒々とうき立たせていました。 「不思議なこともあるものよ」と、美女のいたあたりに再び目を移してよく見れば、そこには何やら理由ありげな古塚が草むしてありました。 「これであったか」と、思わず膝まずき合掌した空山は、やがて立ち上がり、 「面影は程なく消えて跡にただ 田の面に残る草の葉の露」 と、古歌を吟じながら、再び重い杖を諸国巡礼の道に運んだのでした。その行方は誰一人として知る者はなかったのです。 時は流れて四百年、空山の安らいだ小川とその小橋は消えても、里人によって言い継ぎ語り伝えられた物語は今なお生きて、「常盤塚」の名と共に当時を偲ばせているのです。 完 |
|
| ちょっと歴史に戻る | |